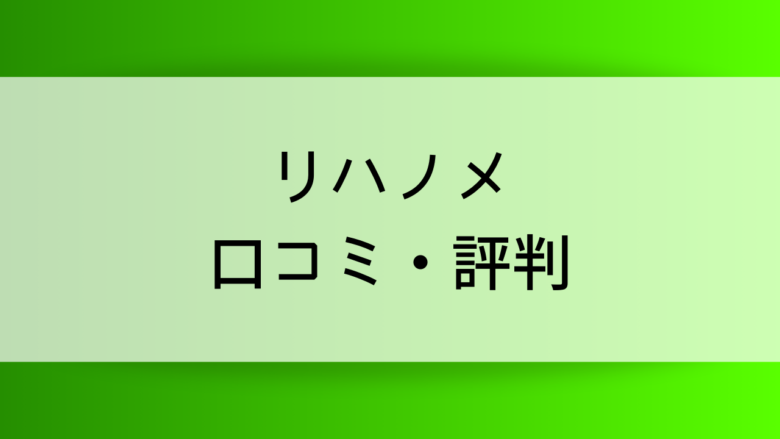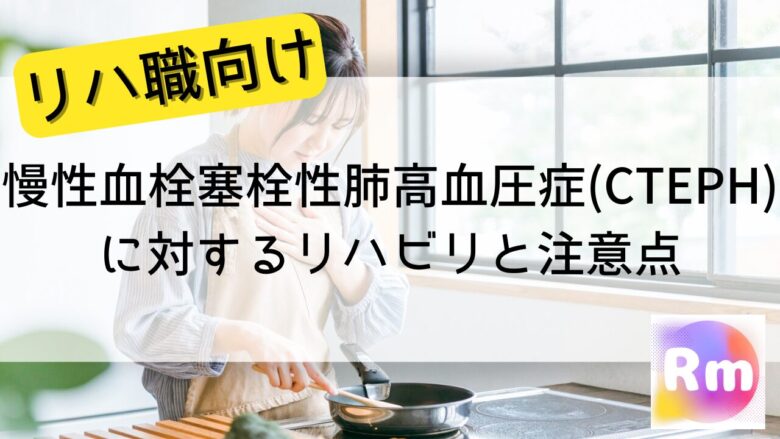DVT(深部静脈血栓症)のリハビリについて【内容や注意点】
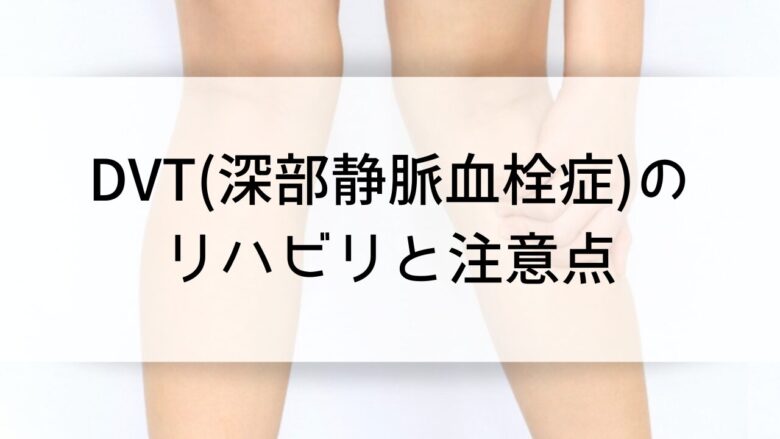

深部静脈血栓症の人のリハビリって、どんなことしたらいいの?気を付けることは?
こんな疑問をお持ちの方に向けた記事です。
結論からいうと、
と言えます。
しかし抗凝固療法を施行していれば,ベッド上安静でなく早期に歩行を行っても,あらたなPTE発症は増加せず,DVTの血栓伸展は減少し,疼痛も改善した591-593).下肢疼痛が強くない,巨大な浮遊血栓を伴わない,一般状態が良好などの条件がそろえば,患者をベッド上安静にせず早期歩行させることにより,DVTの悪化防止と患者のQOLの向上が期待できる.巨大な浮遊血栓症例では症例ごとの判断を要する.
当然、主治医からの指示に従うべきです。
あとは、SPO2モニターでSPO2をモニタリングしながら実施する、というのもポイントです。
下肢遠位の血栓の場合,D-dimerが5µg/mL以上のときは経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)モニター監視下に,5µg/mL未満のときは同モニター監視なしで運動療法を実施する.ただ,どのような場合でもDVTでは,圧迫やミルキングにより血栓が遊離し,PTEへと進展する危険性もあるので,下肢のマッサージは禁忌としている13).
DVT(深部静脈血栓症)に対するリハビリの注意点
DVT(深部静脈血栓症)の方へのリハビリ実施中は、以下の点に気を付けて進めていきましょう。
医師からの指示の確認
「リハビリオーダーあり=無条件に運動OK」ではありません。
「DVT疑い/確定診断あり。リハビリは〇〇(例:ベッド上安静、ベッド上運動可、座位まで可、歩行可など)の指示」といった具体的な指示を確認してください。
不明瞭な場合は、絶対に自己判断せず医師に確認します。
血栓の状態の把握
血栓の部位や状態についても、把握が必要です。
- 部位・範囲: 中枢側(腸骨静脈、大腿静脈など)の血栓ほどPTEのリスクが高いとされます。
- 性状: 特に浮遊性血栓(静脈壁への付着が弱く、血流中に浮いている血栓)の有無は重要です。浮遊性血栓がある場合は、血栓が遊離しやすくPTEリスクが高いため、原則として運動療法は禁忌または厳重な管理下での限定的な運動(例:足関節自動運動のみ)となります。下肢静脈エコー検査の結果を確認しましょう。
- 急性期か慢性期か: 発症からの経過時間も考慮します。急性期(一般的に発症~1,2週間程度)は血栓が不安定な可能性があり、より慎重な対応が求められます。
抗凝固療法の確認
抗凝固療法が適切に行われているかは、運動療法の安全性を担保する上で非常に重要です。
点滴治療や内服状況、またIVCフィルターについても確認しておきます。
ワルファリン投与中
ワルファリン投与中であれば、以下の点に注意しましょう。
- PT-INR(プロトロンビン時間国際標準比)の値を確認: 治療域(目標値、多くの場合2.0~3.0)に達しているかどうかが、離床や運動強度を上げる際の重要な判断材料となります。
- PT-INRが治療域に安定している場合: 医師の許可のもと、段階的な離床や運動強度アップが検討可能となります。
- PT-INRが治療域未満の場合: 抗凝固効果が不十分であり、血栓遊離リスクが相対的に高いと考えられます。離床や積極的な運動はより慎重に、あるいは医師の指示があるまで待機します。
直接経口抗凝固薬(DOAC)投与中
PT-INRのような簡便な効果指標はありませんが、確実に服薬されているか(服薬状況、最終服薬時間など)を確認することが重要です。
服薬が中断されている場合はリスクが高まります。
ヘパリン持続点滴中
APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)などの効果指標を確認します。
下大静脈(IVC)フィルター留置
フィルターは下肢からの血栓が肺へ到達するのを物理的に防ぐ目的で留置されますが、フィルターがあるからといって無条件に運動が安全になるわけではありません。
抗凝固療法の状況や血栓の状態(フィルターより中枢側に新たな血栓がないか等)を考慮し、医師の指示に従います。
抗凝固療法が未導入 / 効果不十分 / 禁忌の場合
原則として、積極的な運動療法(特に患肢の運動や離床)は禁忌です。
絶対安静が必要な場合もあります。
ベッド上での健側運動や、医師の許可があればごく軽微な患肢足関節自動運動に留めるなど、最大限の注意が必要です。
必ず医師に可否と範囲を確認してください。
患者さんの全身状態・下肢状態からの判断
バイタルサイン
運動開始前に安定していることが大前提です。
発熱、頻脈、低血圧、呼吸数増加、SpO2低下などがある場合は、運動を見合わせるか、医師・看護師に相談します。
下肢症状
疼痛、腫脹、熱感、発赤、チアノーゼなどが急性増悪していないかを確認します。
下肢周径を測定し、リハビリ前後で比較することも客観的な評価として有用です。
症状が悪化している場合は、運動強度を下げるか中止し、医師に報告します。
DVTに対するリハビリ【具体的運動とステップアップ】
DVTに対する具体的なリハビリ内容とステップアップについてポイントを解説します。
医師の指示と患者さんの状態に合わせて、段階的に運動を進めます。
以下はあくまで目安であり、個々の状態に合わせて調整が必要です。
【全レベル共通】絶対に避けるべきこと/注意すべき事
- 患肢への直接的なマッサージ、強いストレッチ:血栓遊離の危険性が高いため絶対禁忌。
- 徒手筋力テスト(MMT)での強い抵抗:特に患肢の等尺性収縮を強く求めることは避ける。
- アグレッシブな関節可動域(ROM)訓練:急激な動きや最終域での強い伸張は避ける。
- 息こらえを伴う運動(バルサルバ手技): 胸腔内圧の上昇は静脈還流を阻害し、血圧変動や血栓遊離のリスクを高める可能性があるため避ける。呼吸を止めずに行うよう指導する。
- 血栓部位への物理療法(ホットパック、低周波など)の直接的な適用。
これらのことは、DVTに対して禁忌もしくは非常に危険なので、避けましょう。
運動レベル1:ベッド安静・限定的運動期
- 対象: 抗凝固療法導入直後、PT-INR未達、浮遊性血栓の疑い、バイタル不安定など、リスクが高い状態。医師の指示が「ベッド上安静」または「ごく軽微な運動のみ可」の場合。
- メニュー例:
- 深呼吸、腹式呼吸。
- 健側上下肢の自動運動(ROM維持、筋力維持目的)。
- 患肢の足関節自動運動(アンクルポンプ):ごくゆっくり、軽い力で、疼痛のない範囲で実施。 筋ポンプ作用による血流促進を目的としますが、過度な刺激は避けます。
- リスク回避のポイント:
- 患肢の他動運動、抵抗運動、等尺性運動は原則行わない。
- 血栓部位への圧迫を避ける良肢位保持(ポジショニング)。
- 頻度や回数は最小限から開始。
運動レベル2:ベッド上運動 拡大期
- 対象: 抗凝固療法が安定(PT-INR治療域など)、バイタル安定、医師の指示が「ベッド上運動可」の場合。
- メニュー例:
- レベル1の内容。
- 患肢の股関節・膝関節の自動運動(屈曲・伸展、軽度の外転など、疼痛のない範囲でゆっくりと)。
- 軽いブリッジ運動(殿部を少し浮かす程度)。
- 座位への移行準備としての体幹トレーニング(起き上がり動作練習など)。
- リスク回避のポイント:
- 患肢に急激な負荷や衝撃を与えない。
- 疼痛、腫脹、熱感などが増強しないか注意深く観察。
- セット数や頻度は少なく開始し、反応を見ながら漸増。
運動レベル3:立位・歩行訓練期
- 対象: 状態が安定し、医師から「歩行可」の指示が出ている場合。
- メニュー例:
- 平行棒内歩行から開始し、安定性に応じて歩行器、杖(T字杖など)へと移行。
- 歩行距離、時間、速度を徐々に増加させる。
- 必要に応じて階段昇降練習なども検討。
- リスク回避のポイント:
- 常にバイタルサイン、PTE徴候、下肢症状の変化に注意を払う。転倒リスクにも配慮。
- 歩行中も弾性ストッキングの着用が推奨されることが多い。
- 疲労困憊しない程度の負荷に留める。
DVTに対するリハビリ強度の設定目安
DVTに対するリハビリの強度について解説します。
- 自覚的運動強度(RPE): Borg Scale 6-20段階で 11(楽である)~13(ややきつい)程度 を超えない範囲から開始し、患者さんの反応を見ながら調整。
- 心拍数: 個々の状態によるが、安静時心拍数 +20~30拍/分程度までを目安とするなど、過度な上昇を避ける。基礎心疾患がある場合は特に注意。
- SpO2: 健常者であれば95%以上、COPDなどの基礎疾患がある場合は医師の指示にもよるが、一般的に90%を下回らないように注意。低下が見られたら休憩または中止。
- 時間・頻度: 短時間(例:5~10分/回)から開始し、1日の回数も少なく設定。徐々に時間と頻度を増やしていく。
まとめ
DVT(深部静脈血栓症)に対するリハビリの注意点や運動のステップアップについてご紹介しました。
血栓の部位や、ヘパリン化がなされているかどうか、を確認し、不安があれば直接医師に確認して、リハビリを進めていきましょう。