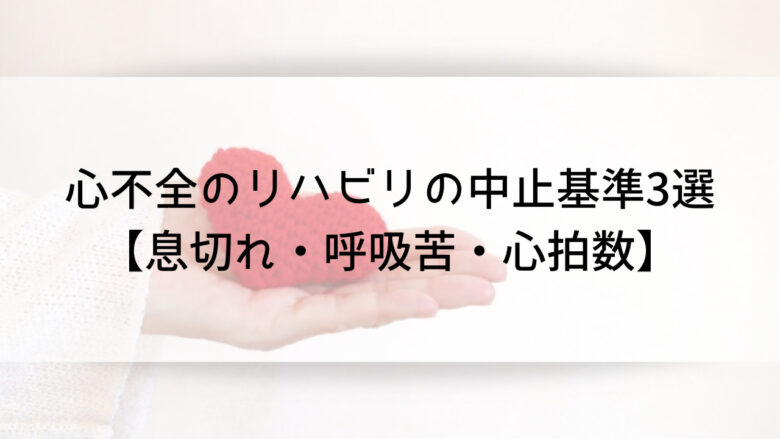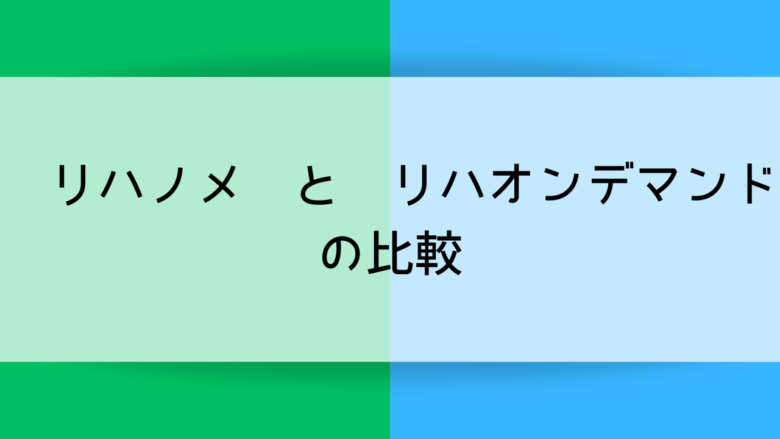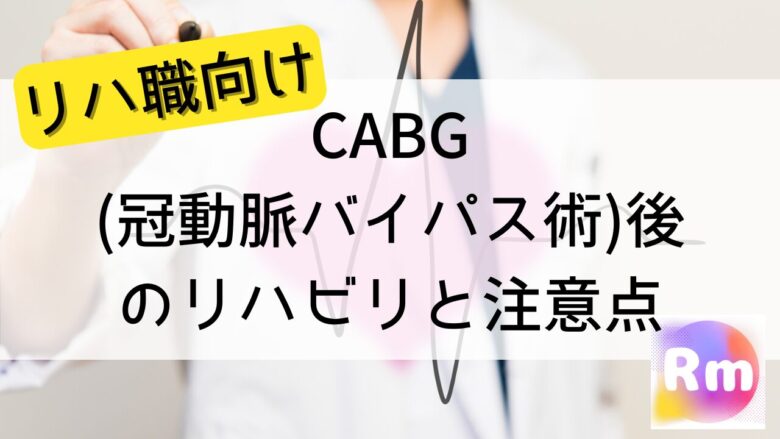横紋筋融解症について【リハビリのポイントや注意点】

横紋筋融解症は、筋肉の広範な損傷により急性腎不全などの重篤な合併症を引き起こす可能性のある疾患です。特に高齢者においては、転倒や長時間の同一姿勢による圧迫が原因で発症するケースが増えており、その後の生活機能の回復には専門的なリハビリテーションと細心の注意が必要です。
この記事では、「横紋筋融解症のリハビリと注意点」という検索意図に基づき、横紋筋融解症の基礎知識から、リハビリテーションの具体的な進め方、そして再発予防のための重要な注意点について、専門的な文献情報に基づいて詳細に解説します。
横紋筋融解症とは:病態と発症原因
横紋筋融解症は、横紋筋の広範な損傷により、筋細胞内の成分(ミオグロビン、クレアチニンキナーゼ(CK)など)が血液中に逸脱し、ミオグロビン尿、高ミオグロビン血症、高CK血症などを呈する病態です。
リハビリ中に筋細胞が回復しようとしている段階で筋肉に負荷が加わってしまうと、筋肉内のエネルギーが不足するケースがあるため注意が必要です。リハビリは、症状の程度に合わせて、負荷量を十分に考慮して行う必要があります。
この疾患の最も重篤な合併症の一つが急性腎不全です。腎不全を伴うと予後が悪くなることが知られています。
多様な発症原因
横紋筋融解症の原因は多岐にわたります。一般的に知られている主な原因には、以下のようなものがあります。
- 外傷
- 激しい活動・運動負荷
- 筋の虚血性変化(血流が滞ること)
- 代謝異常、遺伝性疾患
- 薬物(スタチン系薬剤など)
- 感染(インフルエンザなど)
- 熱中症・悪性高熱などの体温変化
高齢者に特有の発症パターン:長時間の同一姿勢による圧迫
高齢者(65歳以上)の横紋筋融解症において、特に注意すべき原因は転倒・転落による長時間の同一姿勢の保持です。
転倒後に動けなくなり、そのまま数時間、あるいは数日間にわたり不良な姿勢で圧迫が持続することで、下肢などの血流が低下し、筋の虚血性変化(コンパートメント症候群)が生じ、横紋筋融解が誘発されます。
過去の報告では、以下のような長時間の同一姿勢による横紋筋融解症の事例が確認されています。
- あぐら座位(crossed leg sitting posture)での入眠
- 半正座
- しゃがみ
- 右側臥位
- 砕石位(手術中)
- 座位(精神疾患患者)
長時間の下肢への圧迫は、コンパートメント症候群を引き起こすだけでなく、殿部での坐骨神経や膝部での腓骨神経、脛骨神経、腓腹神経などの末梢神経の圧迫性障害を合併させる可能性も指摘されています。
横紋筋融解症と診断された後のリハビリテーション
横紋筋融解症と診断された患者は、筋損傷による筋力低下や麻痺、感覚障害などを呈していることが多く、早期からのリハビリテーション介入が重要となります。
早期リハビリテーション介入の重要性
横紋筋融解症の予後は全体的に良好と考えられていますが、腎不全の有無や基礎疾患によっては機能回復に時間を要する場合もあります。
多くの症例(転倒による症例群)は1カ月以内で退院となることが多いため、廃用症候群が進行しないように早期の離床を進めることが、入院期間の短縮と良好な機能回復に繋がることが示唆されています。
ある報告では、救急搬送後、平均3.5日(1~11日)でリハビリテーションが開始されており、早期からの離床を進めた結果、退院時のADL評価(Barthel Index, BI)の成績(BI gain)が良好であったと考察されています。
リハビリテーションの目標設定
リハビリテーションの目標設定は、患者の入院前の生活形態、残存機能、基礎疾患などを考慮して設定されます。
短期的な目標としては、基本的日常生活動作(起居、移乗、起立動作、排泄)の確立と自立、そして早期の歩行能力の獲得が目指されます。
リハビリテーション結果の指標として、Barthel Index(BI)が用いられます。Barthel Indexは食事、移乗、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、更衣、排便・排尿コントロールの10項目を評価し、合計100点で自立度を評価します。転倒後に横紋筋融解症と診断された14例の検討では、リハビリテーションの結果、退院時BIから入院時BIを引いたBI gainの平均は+28.9点と、概ね良好な結果が得られています。
具体的な訓練内容
横紋筋融解症による麻痺や筋力低下が顕著な場合、主に以下の訓練が実施されます。
- 基本動作訓練: 血液透析が終了し、血清CK値や尿素窒素(BUN)、クレアチニン(Cr)が正常化するなど、医学的状態が安定した段階で、寝返り、起き上がり、立ち上がりなどの基本動作訓練が積極的にベッドサイドで開始されます。
- 筋力増強訓練: 特に麻痺や筋力低下が著しい下肢(あぐら座位の症例では両下肢麻痺、MMTで前脛骨筋、腓腹筋が1)に対して集中的に行われます。
- 起立台、平行棒内での立位保持訓練
- マット上での腰上げ訓練
- 骨盤周囲筋、大腿筋群の筋力強化訓練
- 歩行訓練: 下肢筋力の回復に応じて、簡易短下肢装具(スコッチラップなど)やプラスチック式下腿装具を作製し、下垂足の予防を行いつつ、平行棒内歩行訓練から開始されます。
- 訓練を通じて、伝い歩き〜屋内外歩行の獲得が目標とされます。
- ADL訓練: 移乗動作、排泄動作などの日常生活動作訓練を実施し、ADLの自立を目指します。
回復の具体的事例
長時間のあぐら座位での入眠により両下肢麻痺を呈した73歳男性の症例では、リハビリテーション開始時のBarthel Indexは10点で食事以外の全てに介助が必要でした。しかし、積極的な訓練の結果、3カ月後にはベッドからの起き上がり、立ち上がりが可能となり、平行棒内での歩行も可能となりました。
訓練開始後、徐々に下肢筋力は向上し、腸腰筋5-、大腿四頭筋4-、大腿屈筋5-となり、日常生活動作も向上し、移乗動作、トイレ動作が自立しました。最終的には、SHB装具を装着して歩行器を用いた歩行が可能となり、短期ゴール目標を達成しました。
横紋筋融解症のリハビリテーションにおける重要な注意点
横紋筋融解症の回復を最大限に引き出し、再発や合併症を防ぐためには、医学的な管理とリハビリテーション以外の側面での配慮が必要です。
基礎疾患とリハビリテーション意欲への配慮
横紋筋融解症を発症する高齢者は、アルツハイマー病、認知症(5例)、精神疾患(4例)、パーキンソン病(1例)、脳梗塞後不全麻痺(1例)など、ADLに影響を及ぼす基礎疾患を抱えていることが多いです。
- 訓練意欲の低下: 脳梗塞の再発や痴呆の進行(HDS-R 8/30)により訓練意欲が低下し、目標達成に至らなかった症例が報告されています。また、在宅復帰へのモチベーションが低く、リハビリテーションに消極的であった症例ではBI gainが低く、回復が芳しくなかった例もあります。
- 認知障害や精神疾患への対応: うつ病や認知障害がある症例では、リハビリテーションゴールの設定や獲得が困難となるため、別居家族やケアマネージャーとの連携が不可欠となります。
薬物(服薬)の管理
服薬も横紋筋融解症の発症要因や予後に関連する可能性があるため、注意が必要です。
- スタチン系薬剤: 横紋筋融解症の原因となることが知られており、報告例の中にもスタチン服用者がいました(14例中2例)。
- 多剤服用の影響: 高齢患者において、入院前服薬数が8剤以上の場合、全生存期間が短縮すると報告されています。平均服薬数が5.6剤であった症例群では、回復が良好であった一因と考えられています。抗精神薬や認知症治療薬を服用している症例も多いため、薬剤の相互作用や副作用にも注意が必要です。
不良肢位の回避と再発予防
横紋筋融解症の発症の多くは、長時間の同一不良肢位に起因するため、再発予防が極めて重要です。
- 異常の早期発見: 患者自身が脳梗塞後不全麻痺、前痴呆状態、飲酒などにより、異常感覚や痺痛といった初期異常に気付かず、長時間同一不良肢位のまま入眠してしまうことが状態を悪化させる要因となります。
- 周囲の注意と管理体制: 自ら異常に気付きづらい高齢者や障害者に対して、周囲の人が注意を払い、夜間など支援者がいない時の患者管理体制の確立が必要とされています。
地域連携と独居高齢者への支援体制
高齢者の横紋筋融解症では、独居生活者が多く、転倒後の発見の遅れが重症化に繋がる主要因です。
転倒後に同一姿勢での圧迫が続き発見されるまでに1〜4日を要した症例が多く、14例中9例が独居、または昼間独居でした。
早期の地域連携の必要性
急性期治療やリハビリテーションにより機能が回復しても、独居生活に戻るにはリスクが伴います。入院期間が比較的短く(中央値22.5日)1カ月以内で退院になる症例が多いため、早期から自宅調整をリハビリテーションスタッフと地域の社会制度メンバー間で連携することが必要不可欠です。
具体的には、訪問看護やケアマネージャーを交えた自宅調整が早期に求められます。
社会制度を利用した独居生活の支援
高齢独居者は今後増加すると予想されており、不慮の疾患の発生を防ぐための支援体制が求められます。
- 発見者の役割: 転倒後の発見者は、家族・隣人が57%でしたが、残りの43%は介護保険制度を利用したヘルパーや精神保健福祉相談員によるものでした。これは、社会制度による定期的な訪問や連絡が、命を救う重要な役割を果たしていることを示しています。
- 連絡体制の整備: 独居の高齢者は自宅で倒れると発見までに時間がかかることが予想されるため、家族は定期的に連絡を取り、隣人との日常的な付き合いや社会制度との連携体制を整えておくことが必要です。
まとめ
横紋筋融解症は、特に高齢者においては長時間の不良肢位による圧迫が原因となることが多く、筋力低下や麻痺を伴います。リハビリテーションにおいては、早期の介入(平均3.5日以内)が機能回復(BI gain+28.9点)と入院期間の短縮に繋がります。訓練は、筋力増強、基本動作、歩行訓練が中心となり、装具を使用して下垂足の予防も行われます。
回復を確実なものにするためには、認知障害や訓練意欲の低下などの基礎疾患や精神面への配慮、そして多剤服用のリスクを含む服薬管理が重要です。さらに、独居者が多い現状を鑑みると、転倒後の早期発見と再発予防のために、介護ヘルパーやケアマネージャーを含む地域社会との連携体制を早期に確立することが、患者の安全な在宅復帰に不可欠な注意点となります。
引用・参考文献リスト
本記事は以下の文献を参照し、記述しました。
- 鳴海章人・他: あぐら座位での入隅による両下肢横紋筋融解症のリハビリテーションの経験. リハビリテーション医学 2000;37:467-470.
- 安達幸恵・他: 転倒後に横紋筋融解症と診断された症例のリハビリテーションと地域連携. 日職災医誌 67:350-354,2019.
- 安藤恒三郎: ミオグロビン尿症.新小児医学大系15A.小児運動器病学1(福山幸夫,水野美彦編).中山書店,東京,1986;pp 383-402.
- 菊池臣一,蓮江光男: 下肢のcompartment syndrome.神経内科1983;18:553-559.
- 小西憲子,武下清隆: 長時間の正座入眠により右下肢深部静脈血栓症と横紋筋融解症をきたし急性腎不全となった1症例.日本腎臓学会誌1998;40:22-26.
免責事項
本記事は、理学療法士を対象に CABG(冠動脈バイパス術)術後急性期のリハビリテーションに関する一般的な医学情報をまとめたものです。
個々の患者の状態(心機能、術式、合併症、薬物療法、創部状態など)により、適切なリハビリ内容は大きく異なります。
- 最終的な治療・運動処方は必ず主治医・医療機関の指示に従ってください。
- 本記事の情報を利用して生じた不利益・損害について当方は一切責任を負いません。
- 数値・基準は一般的な目安であり、すべての症例に適応されるものではありません。
- 最新のガイドラインや文献により内容が更新される可能性があります。