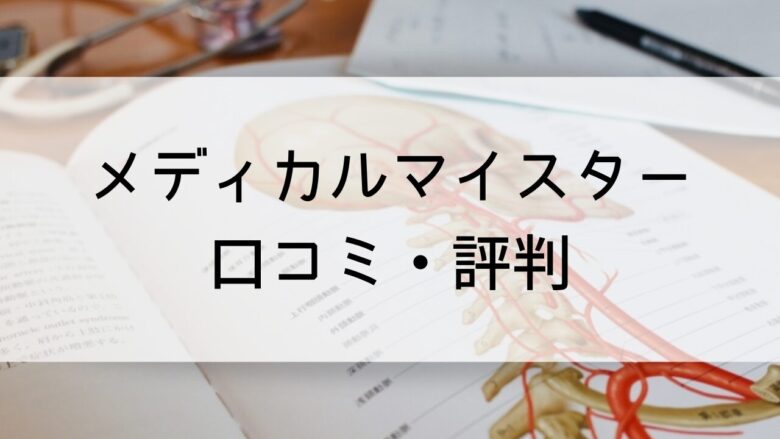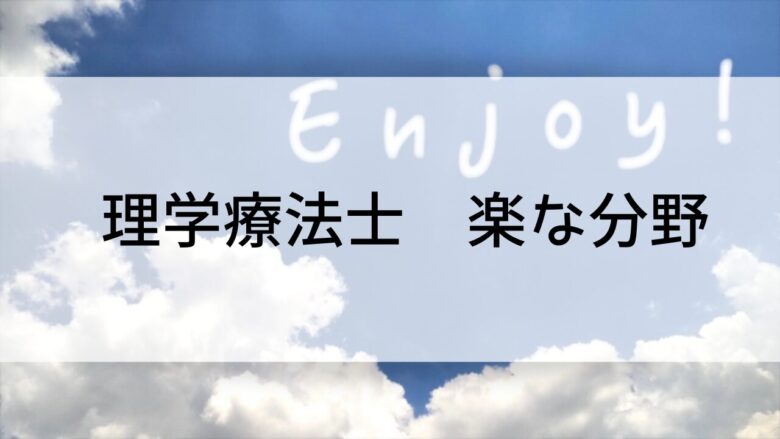【理学療法士向け】「偉そう」と思われないために。患者さんとの信頼を深めるコミュニケーション改善ガイド
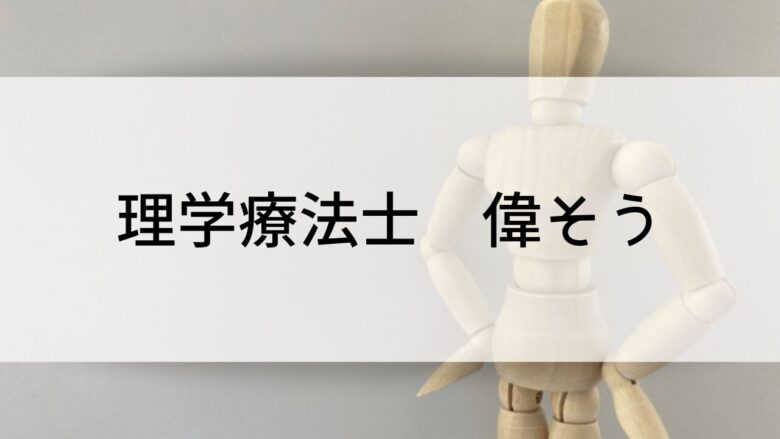
「理学療法士 偉そう」―このような検索キーワードが存在することをご存知でしょうか? 私たち理学療法士は、患者さんの機能回復とQOL向上を目指し、日々専門知識と技術を駆使しています。しかし、意図せずとも、患者さんから「偉そう」「高圧的」と感じられてしまうケースがあるのは残念ながら事実です。
患者さんとの信頼関係は、リハビリテーションの効果を最大限に引き出すための基盤です。もし「偉そう」という印象を与えてしまえば、患者さんのモチベーション低下や、治療への不信感につながりかねません。
この記事では、なぜ私たちが時に「偉そう」と受け取られてしまうのか、その原因を探り、患者さんとのより良い関係性を築くための具体的なコミュニケーション改善策を、理学療法士自身の視点から解説します。日々の臨床を見直し、患者さんからより信頼される理学療法士を目指すための一助となれば幸いです。
なぜ私たちは「偉そう」と受け取られてしまうのか? 自己分析のヒント
まず、患者さんから「偉そう」と思われてしまう可能性のある、私たち自身の言動や態度について、客観的に振り返ってみましょう。
専門家としての自信が「上から目線」に?
私たちは、解剖学、生理学、運動学など、身体に関する高度な専門知識を有しています。その知識に基づき、自信を持って患者さんを評価し、指導することは当然です。しかし、その自信が過剰になったり、表現方法を誤ったりすると、「上から目線」「知識をひけらかしている」と受け取られかねません。
- 専門用語の多用: 患者さんが理解できない専門用語を多用していないでしょうか?
- 断定的な口調: 「これはこうです」「こうしなければダメです」と、一方的に断定するような話し方になっていないでしょうか?
- 説明不足: なぜその運動が必要なのか、その指示にどのような意図があるのか、背景を丁寧に説明できているでしょうか?
指導・指示が「命令口調」になっていないか?
リハビリテーションでは、正しい動作を指導したり、特定の動きを制限したりするなど、具体的な指示を出す場面が多くあります。これらは治療上必要なことですが、伝え方によっては「命令されている」「支配されている」と感じさせてしまう可能性があります。
- 一方的な指示: 患者さんの意見や感覚を聞かずに、一方的に指示を出していないでしょうか?
- 否定的な言葉: 「そのやり方は間違っています」「それでは効果がありません」など、否定的な表現を使いすぎていないでしょうか?
- 声のトーンや表情: 無意識のうちに、厳しい表情や強い口調になっていないでしょうか?
多忙さゆえのコミュニケーション不足
多くの臨床現場では、時間に追われながら複数の患者さんを担当することが少なくありません。その多忙さが、コミュニケーションの質を低下させる一因となることがあります。
- 説明時間の短縮: 時間がないために、説明を早口で済ませたり、省略したりしていないでしょうか?
- 傾聴不足: 患者さんの話を最後まで聞かずに、自分の話を始めてしまっていないでしょうか?
- 表情や態度の硬さ: 忙しさや疲れから、無表情になったり、素っ気ない態度をとってしまったりしていないでしょうか?
患者さんの「感情」への配慮不足
私たちは身体機能の改善に注力しがちですが、患者さんは痛み、不安、焦り、将来への心配など、様々な感情を抱えながらリハビリに臨んでいます。その感情への配慮が不足すると、「冷たい」「寄り添ってくれない」ひいては「偉そう」と感じさせてしまうことがあります。
- 共感の欠如: 患者さんの訴えに対して、「それは仕方ないですね」「気のせいでしょう」など、共感を示さない対応をしていないでしょうか?
- 機能面への偏重: 身体的な側面ばかりに注目し、患者さんの心理的な側面への配慮が欠けていないでしょうか?
無意識の言動や癖
自分では気づかないうちに、相手に威圧感や不快感を与えるような非言語的なサインを発している可能性もあります。
- 腕組みや足組み: 会話中に腕組みや足組みをしていませんか?(状況によりますが、拒絶や防御のサインと受け取られることも)
- ため息: 無意識にため息をついていませんか?
- 視線: 患者さんと適切に視線を合わせていますか?(合わせすぎも、合わせなさすぎも問題)
患者さんとの信頼関係を深めるための具体的な改善策
「偉そう」という印象を避け、患者さんとの良好な信頼関係を築くためには、日々のコミュニケーションにおいて以下の点を意識し、改善していくことが重要です。
丁寧な言葉遣いと「傾聴」の徹底
基本中の基本ですが、常に丁寧な言葉遣いを心がけましょう。馴れ馴れしい言葉遣いや、専門職として不適切な表現は避けるべきです。
- 敬語の適切な使用: 患者さんに対しては、年齢や関係性に関わらず、適切な敬語を使いましょう。
- クッション言葉の活用: 指示や依頼をする際に、「恐れ入りますが」「もしよろしければ」といったクッション言葉を添えるだけで、印象が柔らかくなります。
- 積極的傾聴: 患者さんの話を遮らず、最後まで注意深く耳を傾けましょう。相槌、うなずき、「そうなんですね」「大変でしたね」といった短い応答で、聞いている姿勢を示します。
分かりやすい説明と「理解度の確認」
専門知識を、患者さんが理解できる言葉で伝える努力が不可欠です。
- 平易な言葉への変換: 専門用語は避け、具体的な例えを用いたり、図や模型を活用したりして説明しましょう。
- 説明後の確認: 説明が終わった後には、「ここまでで、何か分からないことや、ご心配な点はありますか?」「今の説明で分かりにくいところはありませんでしたか?」など、必ず理解度を確認する習慣をつけましょう。
「共感」を示すコミュニケーション
患者さんの感情に寄り添う姿勢を示すことで、安心感と信頼感が生まれます。
- 感情の受容: 患者さんの訴え(痛み、不安など)に対して、「お辛いですね」「ご心配ですよね」と、まずはその感情を受け止める言葉を伝えましょう。
- 共感的な言葉かけ: 「〇〇さんはいつもリハビリを一生懸命頑張っていらっしゃいますね」「少しずつですが、確実に良くなっていますよ」など、努力を認め、励ます言葉も大切です。
- I(アイ)メッセージの活用: 指示ではなく、「〇〇していただけると、(私も)嬉しいです/助かります」のように、自分の気持ちを伝える形で依頼するのも有効です。
目標の共有と「協働」意識の醸成
リハビリは、理学療法士と患者さんが協力して進めていくものです。
- 目標設定への参加: リハビリの目的や目標(短期・長期)を一方的に決めるのではなく、患者さんの意向を確認しながら一緒に設定し、共有しましょう。
- パートナーとしての姿勢: 「私たちがサポートしますので、一緒に頑張りましょう」という、対等なパートナーとしての姿勢を示すことが重要です。
非言語コミュニケーションへの意識
言葉以外の要素も、コミュニケーションにおいて大きな影響を与えます。
- 笑顔と穏やかな表情: 意識的に口角を上げ、穏やかな表情で接しましょう。
- 適切なアイコンタクト: 患者さんの目を見て話すことを基本としますが、凝視しすぎないよう注意しましょう。
- 座って話す: 可能であれば、立って見下ろすのではなく、患者さんと同じ目線の高さ(座るなど)で話すように心がけましょう。
定期的な自己評価とフィードバックの活用
自身のコミュニケーションを客観的に見つめ直し、改善していく姿勢が大切です。
- 自己リフレクション: 一日の終わりに、その日の患者さんとのやり取りを短時間でも振り返る習慣をつけましょう。「あの時の説明は分かりやすかっただろうか?」「もっと良い伝え方があったのではないか?」など、自問自答します。
- 他者からのフィードバック: 同僚や先輩・後輩、上司に、自分の対応について意見を求めてみましょう。また、患者さんアンケートなどで寄せられた声にも謙虚に耳を傾け、改善に活かしましょう。
忙しい中でも実践できるコミュニケーションの工夫
時間に追われる中でも、少しの工夫でコミュニケーションの質を高めることは可能です。
挨拶と短い声かけを大切にする
リハビリの開始時と終了時には、必ず笑顔で丁寧な挨拶をしましょう。「おはようございます、〇〇さん。今日の体調はいかがですか?」「お疲れ様でした。今日は特に〇〇を頑張りましたね」といった一言があるだけでも印象は大きく変わります。
重要なポイントは「繰り返す」「メモを活用する」
多忙な中で説明が早口になりがちな場合は、特に重要なポイント(自主トレーニングの内容、注意点など)は、言葉を変えて繰り返したり、最後に要点を確認したりしましょう。必要であれば、簡単なメモを書いて渡したり、患者さん自身にメモを取ってもらったりするのも有効です。
チームでの情報共有と連携
担当患者さんの情報を、医師や看護師、他のセラピストなど、関係するスタッフ間で密に共有しましょう。患者さんの性格やコミュニケーションで気をつけるべき点などを共有しておくことで、チーム全体としてより良い関わり方が可能になります。
まとめ:患者さんに寄り添う姿勢が信頼を生む
私たち理学療法士が持つ専門知識や技術は、患者さんの回復に不可欠なものです。しかし、それを伝える際のコミュニケーションが不適切であれば、せっかくの知識や技術も十分に活かされません。「偉そう」という印象は、決して患者さんのためにならないだけでなく、私たち自身のやりがいをも損なう可能性があります。
この記事で挙げた改善策は、特別なスキルを必要とするものではありません。日々の意識と少しの工夫で実践できることばかりです。常に謙虚な姿勢で学び続け、患者さん一人ひとりの気持ちに寄り添うことを忘れずに、丁寧なコミュニケーションを心がけること。それが、患者さんからの信頼を得て、より質の高いリハビリテーションを提供するための鍵となります。
明日からの臨床で、ぜひ一つでも意識してみてください。患者さんとのより良い関係構築は、必ずや理学療法士としての成長と喜びにつながるはずです。