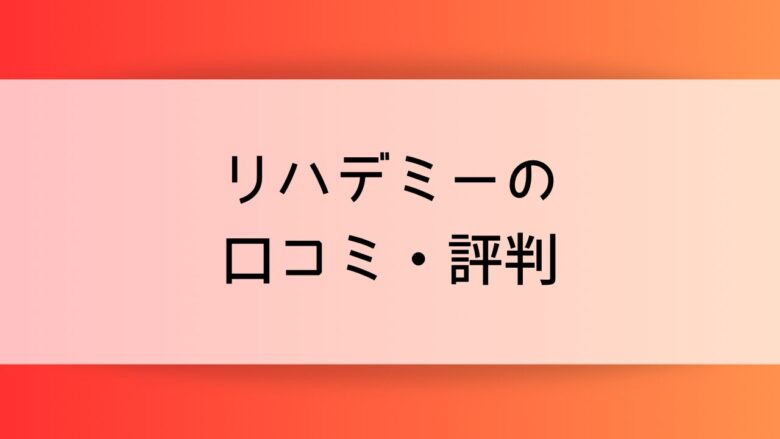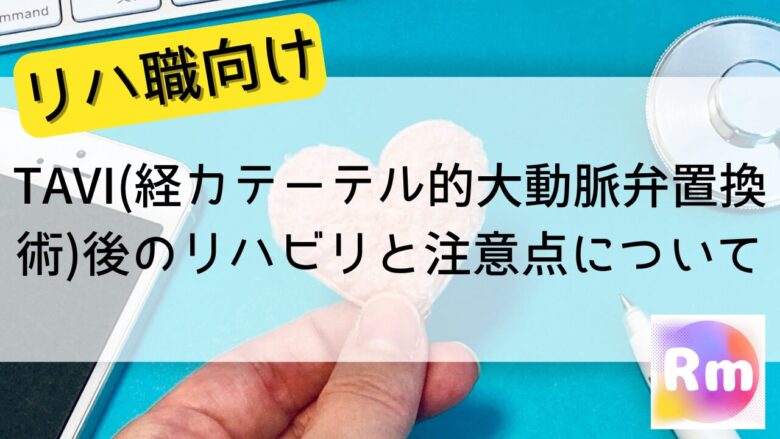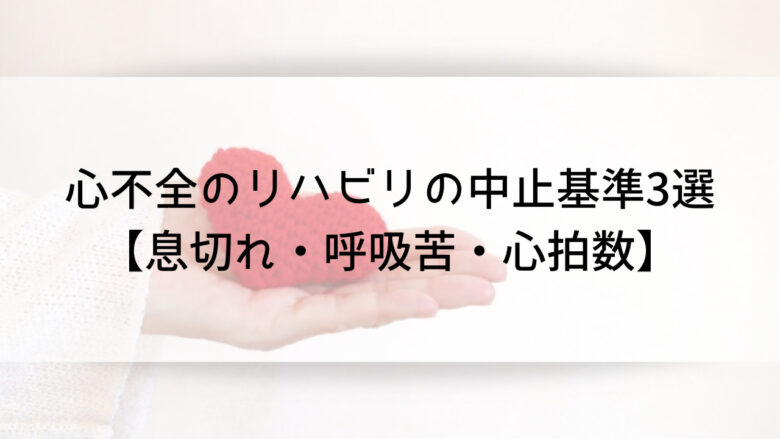【リハビリ職向け】慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)の理学療法や注意点を解説
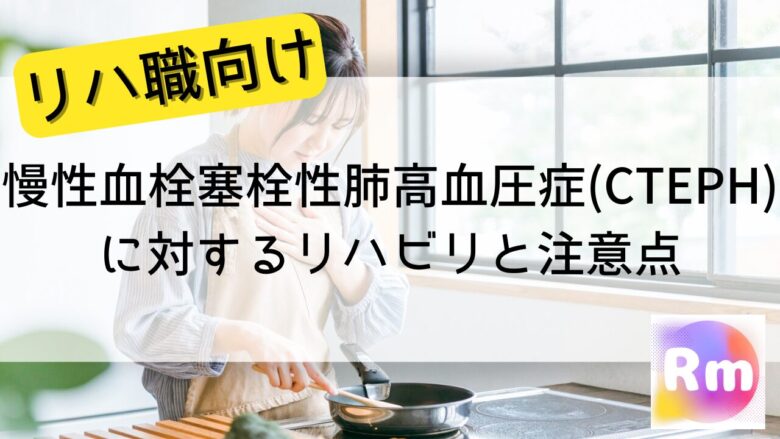
りはスタ運営局
本サイトではアフィリエイト広告を利用しています
慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH:Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension)は、肺動脈内に形成された血栓や線維化によって血流が阻害され、肺血管抵抗が上昇する疾患です。
近年は肺動脈血栓内膜摘除術(PEA)やバルーン肺動脈形成術(BPA)などの外科的治療により、予後は飛躍的に改善しています。
しかし、術前からの低活動・右心負荷・呼吸筋機能低下により、リハビリテーションの重要性はますます高まっています。
本記事では、理学療法士が現場で押さえるべきCTEPHのリハビリ評価・運動療法・呼吸リハのポイントを、術前・術後・在宅フェーズ別に体系的に解説します。
目次
CTEPHとは?リハビリ実践に必要な病態理解
疾患の概要
- 慢性期の肺動脈に器質化血栓が残存し、肺血管の閉塞や狭窄をきたす疾患。
- 結果として右心負荷・心拍出量低下・運動耐容能の著しい低下を引き起こす。
- 一部の患者では「肺血管リモデリング」により非手術性PHが残存し、完全な血流再建が難しいケースもある。
(参考:日本肺高血圧・肺循環学会『肺高血圧症診療ガイドライン2022』)
症状とリハビリへの影響
| 主要症状 | リハビリ上の注意点 |
|---|---|
| 労作時呼吸困難 | 運動耐容能の指標(6分間歩行距離、Borgスケール)としてモニタリング。 |
| 易疲労感 | 運動強度を段階的に設定、無理な負荷は禁忌。 |
| 下肢浮腫 | 右心不全兆候。離床・起立訓練は慎重に。 |
| 失神・めまい | 血行動態不安定時は運動中止。 |
| 酸素飽和度低下 | SpO₂<90%で運動中止を検討。 |
理学療法士が関わる意義
CTEPH患者は“外科的治療+包括的リハビリ”の組み合わせで機能予後が決まります。
| 理学療法士の役割 | 内容 |
|---|---|
| 評価 | 呼吸・循環・筋骨格・運動耐容能・ADL・QOLの多面的評価。 |
| 介入 | 呼吸訓練、早期離床、有酸素運動、筋力トレーニング。 |
| 教育 | 在宅でのセルフモニタリング・抗凝固療法遵守・生活活動指導。 |
| チーム連携 | 循環器・呼吸器・看護・薬剤・栄養士との情報共有。 |
術前リハビリ(Pre-operative Rehabilitation)
目的
- 手術・BPAに備えた呼吸機能・筋力の維持
- 術後合併症(無気肺・筋萎縮・廃用)の予防
- 心肺予備能の改善
評価項目
| 項目 | 評価法 | 意義 |
|---|---|---|
| 呼吸機能 | MIP/MEP、SpO₂ | 呼吸筋トレーニング適応の判断。 |
| 筋力 | 徒手筋力テスト、握力、下肢筋量(BIA) | 筋力低下の程度を可視化。 |
| 運動耐容能 | 6分間歩行、心拍数反応 | 運動プログラム設定。 |
具体的リハ内容
| 項目 | 方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 呼吸筋トレーニング | 1日15〜20分、IMT機器使用(30〜40% MIP) | 過換気・低酸素に注意。 |
| 軽負荷筋トレ | 下肢伸展、スクワット、踵上げなど(RPE 11前後) | めまい・息切れ出現で中止。 |
| 有酸素運動 | 歩行または自転車10〜15分、週3〜5回 | SpO₂ ≦ 90%で負荷減。 |
術後リハビリ(Post-operative Rehabilitation)
フェーズ別進行
| フェーズ | 時期 | 主な目標 | 介入内容 |
|---|---|---|---|
| ICU期(術後1〜2日) | 人工呼吸管理・離脱直後 | 呼吸調整・体位変換・早期覚醒 | 体位排痰・胸郭モビライゼーション・下肢挙上運動。 |
| 急性期病棟(術後3〜10日) | 安静から離床へ | 呼吸筋再教育・立位訓練 | 座位保持→立位→歩行。SpO₂・HRを常時監視。 |
| 回復期(術後10日〜退院) | 運動耐容能・ADL向上 | 有酸素運動+筋トレ | 自転車20分、下肢筋トレ(1RM 30–50%)。 |
運動処方のポイント
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 強度 | Borg 11〜13(軽〜中)または安静時心拍数+20〜30bpm以内。 |
| 頻度 | 週3〜5回(初期は週2から漸増)。 |
| 時間 | 1回20〜30分。ウォームアップ・クールダウン含む。 |
| SpO₂管理 | 90%以下で中止。酸素投与量を調整。 |
| 観察項目 | HR・BP・SpO₂・呼吸数・浮腫・自覚症状。 |
外来・在宅期リハビリ
目的
- 術後体力・呼吸機能の維持
- 再血栓予防・活動習慣化
- 生活の質(QOL)の向上
在宅運動の指導例
| 運動内容 | 目安 | ポイント |
|---|---|---|
| ウォーキング | 1日20〜40分を2回に分ける | 坂道・強風時は回避。脈拍・SpO₂確認。 |
| 呼吸筋トレ | 1日2回、10〜15分 | 過呼吸・めまいに注意。 |
| 下肢筋トレ | スクワット・カーフレイズ | 膝痛・浮腫に注意。 |
| 柔軟体操 | 胸郭・下肢ストレッチ | 呼吸補助筋の柔軟性を維持。 |
患者教育のポイント
- 抗凝固薬(ワルファリン等)の服薬遵守
- 水分摂取と脱水予防
- 長時間の座位回避(血栓予防)
- 息切れ・浮腫・倦怠感など症状出現時は自己判断せず報告
エビデンス・ガイドライン動向
- 日本肺高血圧・肺循環学会器学会(2022)肺高血圧症ガイドラインでは、安定期CTEPH患者に対する運動療法・呼吸リハを推奨。
- BPA/PEA術後の運動耐容能改善効果は多施設研究で確認されている(J-STAGE 2020, Circulation J 2022)。
- 呼吸筋トレーニングは、PEA術後の換気効率改善・6MWD向上に寄与したとの報告あり。
- 右心不全リスク管理と呼吸循環の安全モニタリングを前提に実施することが重要。
よくある質問(Q&A)
Q1. 術直後の離床はいつから可能?
A.再灌流肺水腫がなく、血行動態が安定すれば術後1〜2日で端座位・立位へ進めます。医師指示のもと、段階的に実施します。
Q2. BPA後の運動制限は?
A.BPA施行直後は穿刺部出血や肺出血リスクがあるため、24〜48時間は安静。安定後に軽度歩行から再開します。
Q3. 抗凝固療法中の筋トレは?
A.過度な腹圧負荷(重負荷スクワット、息こらえ動作)は避け、呼吸を意識した低負荷反復法を選択します。
Q4. 退院後の在宅指導で重要なことは?
A.体重・浮腫・息切れ・SpO₂のセルフチェック習慣を指導。
また、再血栓予防として「こまめな歩行」と「十分な水分摂取」が鍵です。
理学療法士が押さえる安全管理チェックリスト
| チェック項目 | 実施基準 |
|---|---|
| 右心不全徴候(浮腫・頸静脈怒張) | 出現時は運動中止。医師報告。 |
| 運動時SpO₂ | 90%以下で中止。 |
| HR・BP反応 | 安静時から+30bpm以上、または血圧低下で中止。 |
| 自覚症状 | 胸痛・めまい・息切れ・倦怠感出現時に中止。 |
| 薬剤調整 | 薬剤変更直後は1週間運動負荷を増やさない。 |
まとめ
- CTEPHは「外科的治療+包括的リハビリ」で予後が変わる疾患。
- 理学療法士は、術前の体力維持・術後の回復促進・在宅での再発予防まで一貫して関与する。
- 運動療法は安全管理を最優先に、SpO₂・HR・自覚症状を常時モニタリング。
- 有酸素運動+呼吸リハ+筋力トレーニングを組み合わせ、段階的に活動量を拡大していくことが重要。
- 患者教育とチーム連携が、CTEPHリハビリ成功の鍵。
免責事項
本記事は理学療法士・リハビリスタッフ向けの教育的情報提供を目的としています。
実際のリハビリ実施にあたっては、主治医・循環器・呼吸器・看護・薬剤・栄養士との連携のもと、患者の病態・術後経過・肺血行動態を十分に評価して行ってください。
ABOUT ME