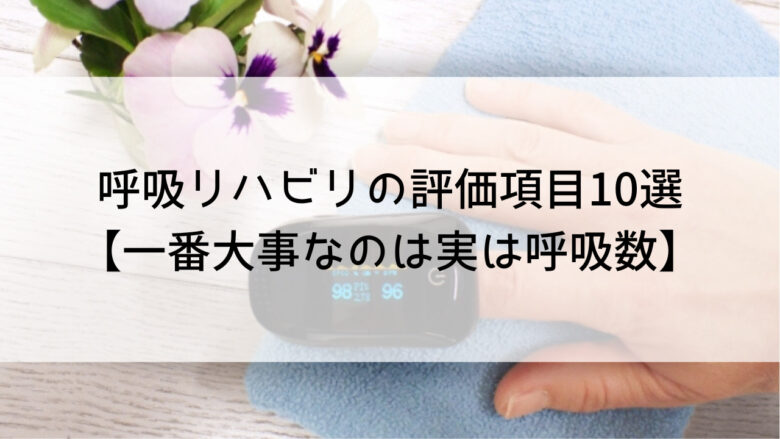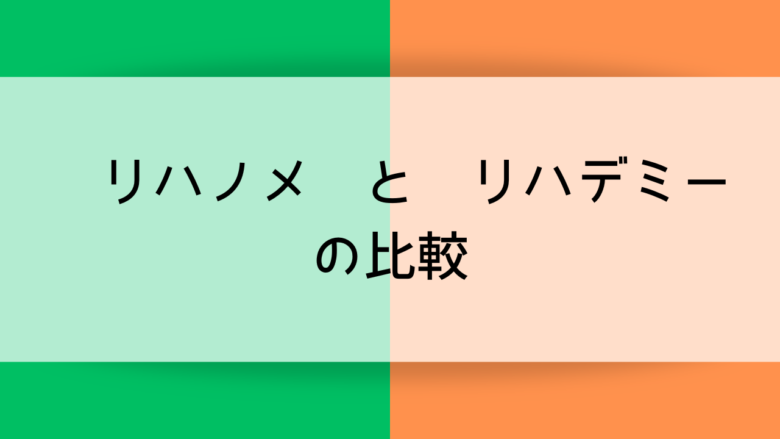【リハ職向け】CABG(冠動脈バイパス術)後のリハビリと注意点
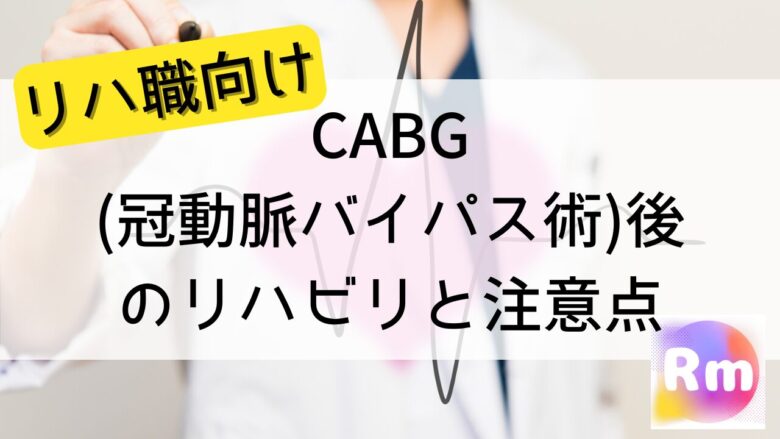
冠動脈バイパス術(Coronary Artery Bypass Grafting:CABG)は、虚血性心疾患に対する代表的な外科的血行再建術であり、術後の適切な心臓リハビリテーションが予後改善・再発予防・身体機能改善に必須です。
本記事では 理学療法士が現場で即使えるレベル に落とし込みつつ、エビデンスに基づいた運動療法・離床基準・評価項目を体系的にまとめました。
CABG(冠動脈バイパス術)後急性期の総論
急性期 CABG のリハビリは、以下の3本柱で構成されます。
合併症の予防
- 呼吸合併症(無気肺・肺炎)が最も多い
- DVT・PE 予防(特に大伏在静脈採取症例)
- 心房細動(AF)や不整脈の発症リスクが高い
- LOS(低心拍出量症候群)による血圧低下
CABG 術後は胸郭の動きが制限され、全麻・人工心肺の影響で換気量が低下し、無気肺を起こしやすい。急性期理学療法は呼吸介入が最重要。
早期離床(術後1〜2日目で開始)
- 術後1日目:端座位 → 立位
- 術後2日目:歩行開始
- 血行動態が安定すれば術後4〜5日目に 300〜500m 歩行が目標
最新心臓リハのエビデンスでは、術後早期離床は肺合併症の低減と在院日数の短縮に有効とされる。早期離床は CABG 急性期リハの中核。
胸骨の安定性を保ちながら活動を拡大
- 胸骨正中切開の影響で上肢を使う動作を制限
- sternal precautions(胸骨注意点)を守る
- 重い荷物・強い押し引き動作は避ける
胸骨は術後6〜8週で癒合。急性期は「胸骨が開かないように」することよりも、「創部痛と動揺を最小限にして安全な動作を学ぶ」ことが重要。
CABG後の初期評価(急性期の必須項目)
少しの変化が重大なイベントに直結するため、以下の項目を毎回チェックしましょう。
循環動態
- 安静時 HR・BP・SpO₂
- 不整脈の有無(PVC、AF)
- 尿量(LOS の指標)
- 末梢冷感・チアノーゼ
CABG 後は β遮断薬により HR が上昇しにくいことがあります。borgスケールなどの主観的運動強度も併用して負荷を見極めましょう。
呼吸状態
- 呼吸数(RR)
- 聴診(crackle → 無気肺、wheeze → 気道狭窄)
- 咳嗽能力
- SpO₂(目標:≥ 95%)
特に crackle が増えた場合は無気肺を疑います。
胸骨・創部の診察
- 発赤・腫脹・滲出
- 胸骨動揺(Sternal Instability Scale)
- 創部痛の程度(NRS)
身体機能
- ベッド上の動作能力(起き上がり)
- 下肢筋力
- 歩行能力
CABG 術後は全身倦怠感・創部痛が強く、簡単な動作でもHR・BPが上昇しやすいです。
CABG急性期の禁忌・中止基準(心臓リハ学会標準)
CABG 後は「負荷量を上げること」よりも、「悪化させないこと」が最優先です。
禁忌
- 安静時 HR > 120 bpm
- SBP ≥ 180 mmHg / DBP ≥ 110 mmHg
- SBP ≤ 90 mmHg(低心拍出を疑う)
- 進行する胸痛
- 重度不整脈(心室性頻拍など)
- SpO₂ ≤ 90%
- 胸骨動揺の増悪
- 発熱・感染兆候
CABG 術後は AF(心房細動)が30%前後で発生します。
HR の急上昇や動悸を認めたら即中止するか、医師に相談しましょう。
運動中止基準
- HR が急上昇(安静+30以上)
- 運動中の SBP の低下(10mmHg以上)
- 顔面蒼白、冷汗
- 過度な息切れ(RPE ≥ 15)
β遮断薬によりHR反応が鈍るため、borgスケール(11–13:軽い〜ややきつい以下)を主軸にするとよいです。
CABG 急性期のリハビリの流れ(術後〜退院)
以下は CABG 標準クリニカルパス(多施設共通)と心臓リハガイドラインに準拠。
術後 0〜1日目|集中治療室(ICU)
早期呼吸理学療法(最優先)
- 深呼吸練習
- 最大吸気保持(IMT/IS 指導)
- 口すぼめ呼吸
- 咳嗽介助(胸抱え法 “splinting”)
CABG は無気肺・肺炎が非常に多いため、呼吸介入は毎回実施。
胸骨痛による咳の抑制を防ぐため、胸を抱えて咳をする方法(splinting)が有効とされています。
循環促進
- 足関節ポンプ運動
- 下肢軽度の自動運動
大伏在静脈採取例は下肢浮腫が生じやすいので、足底背屈によるポンプ運動はDVT予防になります。
離床準備
- ベッドアップ(30〜45°)
- 軽めの端座位保持
- 体動時のHR/BP/SpO₂ の反応を見る
術後 1〜2日目|端座位・立位・短距離歩行
端座位(5〜20分)
- RPE 11 程度を目安
- 呼吸苦・HR・BP を確認
- 軽い下肢運動を追加
立位(1〜2回/日)
- 歩行器 or 杖を使用
- 立位血圧・HR を必ず確認
- 貧血・低心拍出量による立ちくらみに注意
CABG 術後は LOS により立位で SBP が低下する「起立性低血圧」が多い。
歩行開始(30〜100m)
- 心電図モニタ付きの状態で開始
- RPE 11〜13
- 歩行速度はゆっくり
- SpO₂ ≥ 95% を維持
術後 3〜5日目|歩行量の増加・階段練習
歩行距離の目安
- 150〜300m / 日
- 2〜3 セッションに分けて実施
- RPE 11〜12
階段昇降(段差数段〜1フロア)
- 胸骨への上下方向の荷重が増える
- 息切れ・胸部症状・歩行速度の低下に注意
階段はCABG急性期の大きな目標。2段昇降できれば在宅復帰が現実的になる。
胸郭・呼吸エクササイズの継続
- 深呼吸
- ブリージングコントロール
- IS(インセンティブスパイロメータ)
- 咳嗽練習
術後3日目は無気肺がピークになりやすい時期。呼吸訓練を集中的に。
◆ 術後 5日〜退院(7〜10日)
歩行能力の最終調整
- 300〜500m 歩行を目安
- 休みながら歩くのは可
- HR の過上昇に注意(安静+20〜30 以内)
ADL訓練
- トイレ、洗面、衣服交換
- 胸骨を保護する動作の習得(左右対象動作、片側荷重を避ける)
退院前の安全確認
- 上記ADLの安全性
- 階段昇降の可否
- 創部痛・胸骨動揺の評価
- 心不全徴候(浮腫・体重増加)
- 薬物療法(β遮断薬・抗血小板薬)との整合性
CABG 急性期リハのメインテーマ:胸骨管理(Sternal Precautions)
CABG 急性期最大のテーマは「胸骨を守りながら活動拡大すること」。
基本的な注意点
- 5〜10kg 以上の重さを持たない
- 片側で押す・引く動作を避ける
- 大きな上肢挙上を控える
- ベッド起き上がりはローリング法
- 咳嗽は胸抱え法で
- 急な方向転換・転倒を避ける
胸骨制限は施設差が大きく、「過度に厳しすぎると活動量が減る」問題が指摘されるています。
→ 現在は「疼痛・動揺がなければ軽度の上肢使用を許容」する施設も多い。
CABG 急性期に注意すべき合併症とリハ対応
無気肺・肺炎
- 聴診で crackle
- SpO₂ 低下
- 低換気
→ 呼吸介入を強化、早期離床を促進
心房細動(AF)
- 術後 2〜3 日がピーク
- HR急上昇、動悸
→ 運動中止、医師へ報告、安静管理
低心拍出量症候群(LOS)
- SBP ≤ 90
- 冷汗・蒼白
- 冷感
- 尿量低下
→ 運動不可。安静第一。離床は医師指示で調整。
創部不良
- 胸骨動揺
- 発赤・腫脹
- 強い疼痛
→ 上肢負荷を避け、離床レベルを段階的に戻す。
CABG 急性期リハの運動強度設定
有酸素運動(歩行)
- 強度:RPE 11〜13(軽い〜ややきつい)
- HR:安静+20〜30 bpm 以内
- SpO₂:95%以上
- BP:収縮期 90〜160 を目安
運動時間
- 5〜10分 × 2〜3 セッション
- 連続歩行が困難でも分割すれば可
進め方
- 歩行距離 > 歩行速度
- 速度を上げるより距離を優先
- 日内変動(午前に疲れやすい等)を見て調整
まとめ
- CABG後急性期は 呼吸合併症予防が最重要
- 術後1〜2日で離床開始
- 術後4〜5日に 300〜500m の歩行が到達目標
- 胸骨管理(sternal precautions)は疼痛・安定性に基づき個別化
- 禁忌/中止基準を厳密に守る
- HRはβ遮断薬の影響で上がりにくい → RPE中心
- 階段練習は退院前の必須項目
- AF・LOS・無気肺などの合併症に要注意
- ベッド起き上がり・立位・歩行の際は胸骨保護
- DVT予防として下肢ポンプ運動を積極的に
- 在院日数短縮には早期離床+呼吸介入が強く寄与
免責事項
本記事は、理学療法士を対象に CABG(冠動脈バイパス術)術後急性期のリハビリテーションに関する一般的な医学情報をまとめたものです。
個々の患者の状態(心機能、術式、合併症、薬物療法、創部状態など)により、適切なリハビリ内容は大きく異なります。
- 最終的な治療・運動処方は必ず主治医・医療機関の指示に従ってください。
- 本記事の情報を利用して生じた不利益・損害について当方は一切責任を負いません。
- 数値・基準は一般的な目安であり、すべての症例に適応されるものではありません。
- 最新のガイドラインや文献により内容が更新される可能性があります。