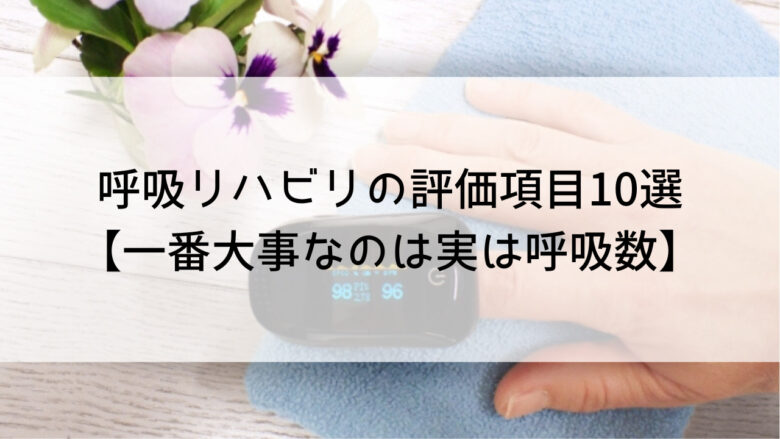【リハ職向け】TAVI(経カテーテル的大動脈弁置換術)後のリハビリと注意点について
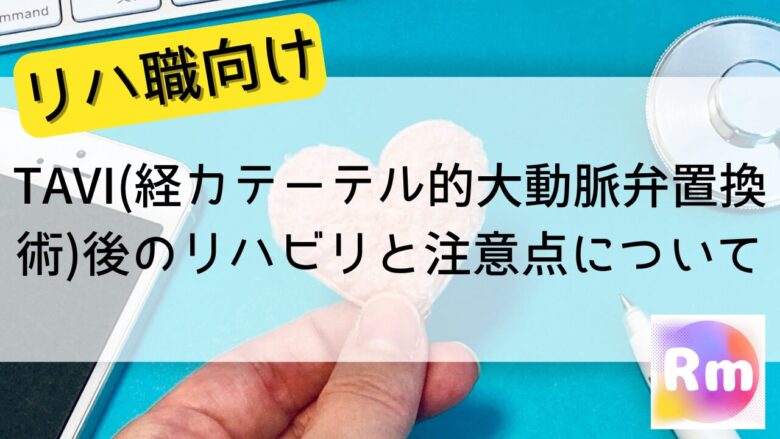
近年、重篤な大動脈弁狭窄症に対して低侵襲に行われる TAVI(経カテーテル的大動脈弁置換術)が急速に普及しています。
高齢・合併症を有する症例が多いため、術後の運動機能低下・筋力低下・フレイルティ・ADL低下を伴うケースも少なくありません。
最新のシステマティックレビューでは術後リハビリ、特に運動療法を含む心臓リハビリが、運動耐容能・機能的自立性・QOL改善に有効との報告があります。
本記事では、理学療法士向けに「TAVI後リハビリ」の目的・適応・タイミング・実際の訓練プログラム・注意点・術後特有のポイント」を整理し、臨床実践で即使える設計・モニタリングの視点も併記します。
対象患者の臨床的特徴
- 高齢者が多く、フレイルや筋力・体力低下、運動耐容能の低下を伴う例が少なくありません。
- 術前に運動耐容能が低下している、前駆的に心不全症状を有していた、ADL低下がある、といった背景を持つ患者も多いです。
- 術後早期から離床・活動開始可能となる症例もありますが、筋力低下・廃用・合併症リスク(大腿動脈アクセス、出血リスク、不整脈など)を慎重に評価すべきです。
リハビリ視点で押さえるべき点
- 侵襲が比較的少ないとはいえ、カテーテルアプローチによる vascular access(例:大腿動脈)や心機能変化(弁置換後の前負荷・後負荷変化)に注意が必要です。
- 術前・術後の運動耐容能・筋力・フレイル・栄養状態・認知・ADL機能を可能な限り評価し、リハビリプログラムを個別化することが求められます。
- 多職種(循環器内科・心臓血管外科・看護・栄養・理学療法・作業療法など)との連携が不可欠です。
リハビリテーションを行う意義(エビデンス)
主なエビデンス
- 最近のメタ解析・システマティックレビューでは、TAVI後に運動療法を含む心臓リハビリ(CR: cardiac rehabilitation)を行った群では、6分間歩行距離(6MWT)やBarthel Index(BI:日常生活動作尺度)で有意な改善が認められています。 (PubMed)
- 日本国内データでも、入院中の心臓リハビリ実施が入院関連廃用(hospital‐associated disability : HAD)予防に関連するという報告があります。 (agsjournals.onlinelibrary.wiley.com)
- また、理学療法的な観点からも、重症ASあるいはTAVI前後で運動介入を行う可能性がある旨が報告されています。 (PMC)
意義まとめ
- 運動耐容能・筋力・日常生活動作(ADL)・QOL(生活の質)の改善が見込まれる。
- 高齢・合併症ありのTAVI症例において、廃用・筋萎縮・体力低下を予防・改善できる可能性がある。
- 早期離床・活動再開を促すことで、長期的な転帰改善(再入院・ロングターム機能低下予防)に寄与しうる。
- 理学療法士が介入することで、術後の身体機能低下・フレイル進行を抑える役割が期待される。
留意点
- ただし、最適な開始時期・強度・プログラムの詳細については、現時点では明確なガイドラインが充分確立されていないという報告もあります。 (MDPI)
- 患者個体差(年齢・合併症・術式・術前機能)によるばらつきが大きいため、理学療法士は個別評価・モニタリングを慎重に行う必要があります。
理学療法士が押さえるべき術後評価項目
術後のリハビリプログラムを設計・モニタリングするために、以下の評価項目を理学療法士として確実に実施・記録することを推奨します。
| 項目 | 内容・目的 | 補足 |
|---|---|---|
| 安定期の確認 | 術直後:血行動態の安定(血圧・心拍・弁機能・アクセス部位出血・合併症有無)確認 | 循環器・心リハに確認を。 |
| 運動耐容能 | 6分間歩行テスト(6MWT)、階段昇降時間、歩行速度 など | メタ解析では6MWT改善が示されている。 (PubMed) |
| 筋力・筋⾁量 | 下肢筋力(例:立ち上がり回数、膝伸展筋力)、握力、筋萎縮の有無 | 高齢例で下肢筋力低下が多いため注意。 |
| フレイル/サルコペニア指標 | 歩行速度、握力、体重減少、活動量低下 など | TAVI対象の高齢例ではフレイル合併例も多い。 |
| ADL/日常生活動作 | Barthel Index (BI)、改訂版日常生活動作スケール、階段昇降能力など | BI改善も報告あり。 (PubMed) |
| 栄養・体組成 | 体重・BMI・筋⾁量・栄養評価(例:MNA) | 筋力維持・回復に関連。 |
| 心機能/弁機能確認 | 主治医・循環器の所見による弁圧較差・心機能(EF・心拍数・心雑音など) | 活動量上昇に伴う負荷を知るため。 |
| サイコソーシャル/QOL | 疲労感・抑うつ・セルフケア能力・QOLアンケート(例:SF-12等) | メタ解析ではQOL改善も示唆。 (リッピンコット) |
これらを術後早期(入室前評価)、入院中/退院時、退院後(1 ~ 3 ヶ月後)と区分して評価・再評価することで、介入効果・プログラム修正の根拠が得られます。
リハビリプログラム設計(フェーズ別)
理学療法士がTAVI後リハビリを設計・実施する際、「術直後→中期→退院後」のフェーズに分けると整理しやすいです。以下に各フェーズ別のポイント・実際内容・留意点を整理します。
術直後(ベッドサイド〜早期離床期)
目的:術直後の身体機能低下・廃用進行を防ぎつつ、安全に離床・歩行開始へ繋げる。
開始時期の目安:術翌日〜数日以内(施設・患者状態により異なる)
- ベッド上訓練:四肢求心・遠心運動、ストレッチ、関節可動域維持、深呼吸・体動訓練
- 起き上がり・座位・立位練習:早期立位を促す(循環・出血・血圧変動確認)
- 出血・アクセス部位(大腿動脈等)観察を兼ねたウォーキング開始(病棟内)
負荷・強度:心拍数上昇・血圧変化を観察しながら “安静時+10~20拍/分以内”、RPE(自覚的運動強度)軽度〜中等度目安。
理学療法士の視点: - 大腿アクセス利用例では、安静時出血・皮下出血・床ずれリスクに注意。
- 心機能がまだ変動する時期のため、1回あたりの歩数・距離・時間は少量から開始し徐々に増加。
- 術前筋力低下例・フレイル例では、下肢筋力維持を目的とした筋収縮(アイソメトリック)も併用検討。
入院中回復期(中期)
目的:歩行距離・歩行速度・筋力の回復、日常生活動作(ADL)自立度の向上、退院準備。
開始時期の目安:術後入院2〜10日以降〜退院直前まで(施設により異なる)
- 有酸素運動:病棟・リハビリ室歩行、エルゴメーター(条件による)、階段昇降訓練
- 筋力トレーニング:スクワット(補助付き)、立ち上がり練習、レッグプレス系、体幹強化、下肢・上肢筋群の抵抗運動
- バランス訓練・転倒予防運動
- ADL練習:入浴動作・トイレ動作・歩行・階段昇降など日常動作再獲得
- リスク因子教育:運動指導・生活指導・体重管理・栄養連携(多職種)
負荷・強度:運動負荷・時間を徐々に拡大。心拍数・血圧・症状(めまい・息切れ・浮腫)をモニタリング。
理学療法士の視点: - 文献では、運動系CRプログラムによる6MWT・BI改善が報告されている点を踏まえ、歩行距離や立ち上がり能力を定期的に測定する。 (リッピンコット)
- フレイル・栄養低下例では、筋力維持・増強+栄養アプローチ(栄養士連携)も重要。
- 出血リスク・血管アクセス部位のトラブル(偽動脈瘤・血腫)に対する観察も継続。
- 心機能の回復具合・合併症(ペースメーカー植込み後等)によっては、負荷調整が必要。
退院後・外来フォロー期(後期)
目的:社会復帰・活動レベルの拡大・長期的な機能維持・再入院予防。
開始時期の目安:退院直後〜3〜6ヶ月、あるいはその後も継続的に。
- 有酸素運動:ウォーキング、サイクリング、軽度ジョギングなど(施設・フィットネス併用可)
- 筋力トレーニング:自宅・フィットネスでの自立運動(レジスタンスバンド、体重負荷運動)
- グループ運動・心臓リハ(CRプログラム/通所型)参加
- 生活指導:定期運動習慣化・栄養・体重管理・喫煙・飲酒・メンタルヘルス
- フレイル予防:筋力・活動量維持・社会参加支援
負荷・強度:中等度~やや高めの運動まで段階的に。定期的に6MWT・歩行速度・筋力を再測定。
理学療法士の視点: - 文献では退院後3〜6ヶ月以内のCRプログラム介入によってQOL・生活機能改善が確認されています。 (リッピンコット)
- 長期的フォローを見据え、患者自身による運動継続習慣化の支援と、モチベーション維持策(運動記録・フィードバック)を構築。
- 合併症(心不全再発・不整脈・アクセス部位トラブル)有無のモニタリング継続。循環器・心リハチームとの連携を継続する。
注意すべき合併症・モニタリングポイント
理学療法士として安全に介入するためには、以下の点に注意・モニタリングが必要です。
主な注意点
- アクセス部位出血・血腫:大腿動脈・他アプローチ利用例では特に初期離床・歩行時に注意。
- 心機能変化・血行動態の変動:大動脈弁狭窄が解除されることで、前負荷・後負荷が変化します。運動開始時の心拍数・血圧・酸素飽和度・症状(めまい・息切れ・胸痛)を厳格に観察。
- 不整脈・ペースメーカー植込み例:術後ペースメーカーが植込まれた場合や、術中ブロックが発生した症例では、運動時の心拍応答に注意。
- 転倒・筋力低下・廃用:高齢例で筋力低下・バランス障害により転倒リスクが高いため、バランス訓練・立ち上がり反復・歩行訓練を慎重に行う。
- フレイル・栄養不良・サルコペニア:これらが併存していると回復遅延・運動介入反応低下の可能性あり。筋力訓練+栄養アプローチが必要。
- 長期予後リスク:文献により、TAVI後の早期リハビリ開始・期間・歩行距離延長などが生存や機能予後に関連するとする報告あり。 (リッピンコット)
モニタリング指標例
- 歩行距離(6MWT)/歩行速度/階段昇降時間
- 下肢筋力(立ち上がりテスト回数・トイレ動作速度など)
- 筋肉量・握力・バランス能力
- ADLスケール(BI等)
- 心拍数・血圧・症状出現(胸痛・めまい・浮腫)
- 運動中・運動後の疲労・息切れ(Borg RPEスケール)
- 定期的な再評価(術前、術直後、退院時、退院後3〜6月)
フレイル・高齢・多合併症例での工夫・実践のコツ
TAVI対象患者は「高齢」「フレイル」「合併症多め」という特徴を持つことが多く、理学療法士としては以下のような実践的工夫が有効です。
- 開始負荷・進行スピードを慎重に:筋力弱・貧血・骨粗鬆症・関節疾患など併存例では、立ち上がり回数少なめ・歩行距離少なめからスタートし、丁寧なステップアップを。
- 筋力訓練+バランストレーニングを積極的に:歩行速度向上だけでなく、転倒リスク低減・下肢筋力改善を狙うため、スクワット補助付き、ステップ台、片脚立ち、レジスタンスバンドなどを導入。
- 栄養・身体活動量管理を併用:栄養士・看護師と連携し、筋肉量維持・体重減少予防・活動量維持をセットで考える。
- モチベーション維持・運動習慣化支援:高齢例では「やらされ感」にならないよう、患者の生活背景・動機付けを聴取し、セルフエクササイズを日常動作に組み込む。
- 家庭・地域フォロー体制を検討:退院後の継続が鍵。地域の通所型心リハ施設・運動教室・地域包括ケアと連携して「運動-生活活動」の橋渡しを。
- 多職種チームでの連携重視:循環器・心リハ、看護、栄養、薬剤師・ソーシャルワーカーと定期的なカンファレンスを行い、安全に機能回復を促進。
FAQ/よくある質問
Q1. どのくらいの時期から歩行訓練を開始すべきですか?
A1. 患者の状態によって異なりますが、術翌日~術後数日以内に離床・座位・病棟内歩行を開始する施設もあります。アクセス部位や術中‐術後の合併症を確認しながら理学療法士・主治医・心リハチームで調整することが重要です。
Q2. 負荷設定(心拍数・秒数・距離)はどうすれば良いですか?
A2. 文献的には「軽度~中等度」が安全域とされており、例えば安静時心拍数+10~20拍/分、またはRPE (自覚的運動強度)で「ややきつい」程度以内を目安に段階的進行が推奨されます。個別状態・心機能・合併症に応じて調整を。
Q3. 筋力トレーニングはいつから始めて良い?
A3. 非侵襲性TAVIの特徴を踏まえ、早期から軽負荷にて筋力訓練を開始しても良いという考えが増えています。例えば座位立脚運動・補助付きスクワット・レッグプレス軽負荷などを術後中期には導入し、下肢筋力維持・改善を図るのが理想です。
Q4. 外来・地域でのフォローはどう組めばよい?
A4. 退院後は、自宅運動+地域心リハ・運動教室・フィットネス併用が効果的です。歩行距離・速度・筋力を定期的に測定・記録し、運動継続のモチベーション維持策(運動日誌・グループ形式)を組むと良いでしょう。
Q5. 高齢・多疾患例では何を特に気を付けるべき?
A5. フレイル・サルコペニア・骨粗鬆症・関節疾患など併存例では、過剰な負荷をかけず慎重に進行することが重要です。また、転倒・骨折リスク・筋萎縮への対応を前提に、バランストレーニング・転倒予防・活動量拡大支援まで視野に入れる必要があります。
まとめ
- TAVI後の理学療法介入は、運動耐容能・筋力・ADL・QOL改善に有効であり、理学療法士として介入価値が十分にあります。
- 術直後から退院後・地域フォローまで、フェーズに応じたプログラム設計が鍵です。
- 多職種連携・個別評価・モニタリング・安全な負荷設定を理学療法士が担うことで、患者の機能回復・生活復帰を支援できます。
- 高齢・フレイル・合併症例においては、特に慎重な進行管理・筋力・バランス・転倒対策が重要です。
- 今後、TAVI対象のリハビリに関するガイドラインや大規模データも増えており、理学療法士として最新知見をキャッチアップすることが望まれます。
免責事項
本記事は理学療法士向けに一般的知見をまとめたものであり、特定の患者様に対する診断・治療・リハビリテーションプログラムを個別に指示するものではありません。実際のリハビリ実践にあたっては、必ず主治医・循環器・心リハスタッフ・多職種チームと連携し、患者様の状態・合併症・施設条件を踏まえて安全に進めてください。